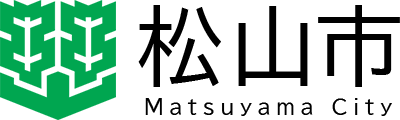第15回坊っちゃん文学賞ショートショート部門子規・漱石特別賞「はるのうた」
更新日:2018年3月1日
PDFでもお読みいただけます。
「はるのうた」 松山 帖句
ピンク色のもち米を包み込む葉の緑が眩しい。日本人というのは、どうしてこうも桜が好きなんだろう。葉っぱまで食べるなんて。
ハア。
いいや。好きという気持ちに理由なんてないのだ。それは朝になったら太陽が昇るように、夜になったら月が浮かぶように、ただそこにあるから、ただそこにいるから好きになってしまうのだ。
フウ。
「惑星のふうと吐く息春の風」
「え?」
「春ちゃんのおかげでええんができたわい」
いつの間にかテーブルの向かいに座っていた祖母がさらさらとノートの上に万年筆を走らせる。つい最近、八八歳の誕生日を迎えたばかりの祖母の趣味は俳句で、いつもこうやって思いついた句があればすぐにノートに書き足していく。傍らには晩御飯の用意に使った絣のエプロンが綺麗にたたまれてあった。
「それより、さっきからおやつ眺めてため息ぎりつきよるが、どうぞしたんかね」
祖母が言った。土曜日はいつも残業で遅くなる母の代わりに、祖母が私たちの御飯を用意してから句会とやらに出かけていく。
「ん?別に。何もないよ」
「食べんの、桜餅?」
「うん、あんまり食欲がないかも」
「どしたん?本を読むことと食欲だけは誰にも負けん春ちゃんやのに」
祖母は私のおでこに手を当てた。
「おばあちゃん、大丈夫やって」
今の私にとってもう食べることはさほど重要ではなくなってしまったのだ。
「ありゃりゃ、こりゃ大変じゃ」
「はあ?」
「恋煩い!」
祖母は、あははと笑った。
「そんな、してないよ恋なんか」
頬が熱いよ。
「恋はね、するもんやのうて、落ちるもんよ」
そう言って祖母がまた、あははと笑った。
「で、どんな子なん?春ちゃんが好きになった子は」
「ええ?もう、だから違うって」
「今度、日切焼きの黒ごまクリーム入り買って来てあげるけん」
「本当に?」
前言撤回。食べることは、人間の大事な営みの一つだ。そして、私の秘密なんて所詮、日切焼き三ケ分くらいの重さしかない。
「ええとね、めっちゃかっこいい子で」
「ほう」
「やけど、他の女子もみんな好きやと思う。ピッチャーとかやってるし」
「野球部かね。そら人気があるわい」
「うん、やけん私なんか絶対無理よ、そんな可愛いくもないし」
「こーりゃ」
祖母がコツンと優しくげんこつをくれた。
「若いおなごの子がそんな後ろ向きでどうするんよ」
「だってえ」私はテーブルにうつ伏せになり「私、超文系やしい」と、いじけ虫のように体をよじらせた。火照った頬にテーブルのツルツルがあたる。冷たくて気持ちいい。
「鞦韆(しゅうせん)は漕ぐべし、愛は奪うべし!」
「え?」
「三橋鷹女」ピンと祖母の背筋が伸びた音がした。品のいい高笑いが居間に響く。
そうだ。私はここに文系女子の権化のような人がいたのをすっかり忘れていた。
祖母は昭和の初め、まだ女性が進学をして勉強をするということが珍しい時代に県立松山高等女学校に通った才女だった。
「春ちゃん、文系には文系なりの戦い方っちゅうもんがあるんよ」
「戦い・・方?」
「そうよ、恋は奪うべし!」そう言うと祖母は「腹が減っては戦はできぬ」と桜餅を、まるで豆でも放り込むようにポイと口に投げ入れた。祖母は自分と同じ名前の付いたその餅を食べると不思議と力が湧いてくるといつも言っていた。それは私が春という季節が一番好きということと何となく似ているのだなと思った。私もつられて、餡の程よい甘さと桜葉の塩っぱさが絶妙のその桜餅を頬張った。
「で、春ちゃん」祖母が言った。
「直接告白するっていうのはどうなん?」
「はあ?絶対無理!」
私にとってそれはまるでエベレストの山に無酸素で登頂するぐらい無謀に思えた。
失敗すれば命を落とす。
さすがにその気持ちは祖母も理解してくれた。そこで手紙がいいのではないかと言った。
「ほれ、若い人はその小さい電話でやっとるんやろがね」
祖母は私の携帯電話を指差した。
「え?やけど私、その子のメアド知らんし」
「冥土って何?あの世?」
「冥土じゃなくてメアド。メールアドレス。それがないと手紙を送れんのよ」
「ふーん、じゃあ、そのメイドアドレスとか言うのを教えてもらいや」
「そんなん恥ずかしいし、絶対無理やわ。それにメールで告白するんも、直接言うんも変わらんやん、絶対無理」
「もう、無理無理無理無理て。じゃあ、どうするん?」
「そんなん、わからんわ」
「もしも」祖母の声が急に強くなった。
「今戦争になって、春ちゃんの思いを伝えきれずにその子が死んだら、ずっと、一生後悔することになるんよ」
「ちょっとおばあちゃん、私の好きな子を勝手に戦争で殺さんといてや」
祖母の話があまりに大げさ過ぎて私は笑ってしまった。だけど祖母は笑わなかった。どこか違う時代に迷い込んでしまった迷子のような、悲しい顔をしていた。
「おばあちゃん?」
私が呼ぶと「なあに?」といつもの祖母が答えた。私は気を取り直して言った。
「じゃあさ、おばあちゃんの時はどうやったん?どうやっておじいちゃんに告白したん?」
祖母の部屋の、お世辞にもハンサムと言えないが、人の良さが滲み出ている祖父の写真。
「私かね?私の時は好きとか嫌いとかなかったからねえ。結婚は家同士で決めるもんやったんよ」
「はあ?何それっ、本当?」
祖母は大きく頷いた。
「ええ、信じられんそんなん。ほんなら、おじいちゃんのことは?好きじゃなかったん?」
「好きにも色々な好きがあるけんねえ」
「え、どういうこと?何、色々な好きって?」
「そんなことより」祖母が笑う。
「俳句はどう?」
「は、俳句?」いきなりトンチンカンなことを言うのでびっくりした。
「俳句が、どしたん?」
「恋文よ」
「こい、ぶみ?」
おばあちゃん曰く、その昔、俳句は好きな相手のことを詠んで、恋文として相手に送ることもあったそうだ。
「やけど、手紙がめっちゃ短くなっただけで、結局は手紙と変わらんやん、恥ずかしいわ」
「相手にばれんように詠むんも、俳句の醍醐味やがね。何せ世界で一番短い詩やけんね」
県女の四十五期生は不敵な笑みを浮かべ、お茶をズズズッとすすった。
「で、彼の名前は?」
「・・・風早くん」
「かぜ、はや?」
「うん」
「ほうかね、かぜはやくん言うんかね」
「うん」
「ふーん、かぜはやねえ、かぜはや、かぜ、風・・・ああ、なるほどね。これがええわい」
祖母がうんうんと一人頷いた。
「え、なになに?何がええん?」
「あのね」祖母の笑った顔が可愛らしい少女に見えた。「春ちゃん、まずは“風光る”で始まる俳句を考えよか」
「風光るって何?」
「春の季語よ」
「季語?ふーん。やけどおかしない?風が光るって。風は普通、吹く、やないん」
「まあ、春ちゃんもそのうちわかるようになるけん。はい、ほんなら残りは十二音やから」
「いやいや、ちょっと待って。私、本当に俳句とか作るん無理やって。そんな興味ないし」
「外にも出よ触るるばかりに春の月」
祖母が言った。
ん?
「今度は誰なん?」
「中村汀女」
なんか。
「なんか、ええね」
「そう?好き?」
「うん、なんか、好き。私の名前も入ってるし」
祖母が「そういうことかね」と笑った。
私は、へへへと頭を掻いた。
「春ちゃん、俳句を詠むということは、色々なものを自分で見て、聞いて、感じて、それを心の翻訳機を使って五七五の十七音に転化させるということなんよ。そんで、そのためには自分の足で外に出て行かないかん。私は俳句を作ることで、春ちゃんが今いるところからちょっとでも外に踏み出すことができたらええかなあと思うんよ。そりゃあ外に出たら失敗もある。やけど、それ以上のええことがたくさん待っとるよ。見とおみ」祖母はそう言って私の頭をギュッと抱きしめた。
「私は外に出たら、こんなに可愛い春のお月さんに会えたがね」
祖母の手からふんわりと香ばしいいりこの匂いがした。
「おばあちゃんのいりこ出汁のシチュー、私、めっちゃ好き」
「ありがと。お母さん帰ってきたら一緒にお食べ」
次の日から、私は祖母に俳句を習い始めた。
と同時に、祖母と私は風早くんに告白するために、ある壮大な計画を練った。
その計画とは、クラスで季節ごとに作る学級新聞に俳句のコーナーを作ってもらい、自作の俳句を三句ずつ発表する。そして一年後、春夏秋冬合わせた十二句全部の上五の句(五七五の一番始めの5音)の頭文字一つずつを抜き出すと、風早くんへの十二文字の恋文が完成するという仕組みだ。風早くんやみんなにバレないどころか、永遠に気づかれないかもしれない。しかし、私にとっては、このやり場のない好きという気持ちを形にするという行為にこそ意味があり、それを考えた祖母の底知れぬ文系乙女度には改めて恐れ入った。
私は早速一人俳句部を立ち上げ、春季学級新聞に作った句を載せてもらった。クラスの何人かは「へえ、俳句やってるんだあ」と声をかけてくれたがそれはみんな女子で、風早くんを含む男子は一切の関心を示さなかった。
年が明けてしばらくした頃だった。祖母が風邪から肺炎をこじらせ入院をした。容態は良くなるどころか、ご飯もまともに食べられない状態が続いた。八八歳の体はお見舞いに行くたび、どんどん小さくなっていった。
「私、おばあちゃんと同じ高校受けるんよ」
そう言うと、祖母は嬉しそうに笑った。そして、「俳句は?」と吹けば消えてしまいそうな声で言った。
「バッチリよ。今日、冬の俳句を掲示して来たけん」私は祖母に小さくピースをした。
「桜しべ降るプロ・・・」
「え?」
「桜しべ降る、プロローグ、始まりぬ」
ありったけの力を振り絞るようにして祖母は自作の俳句を詠んだ。
「おばあちゃん、“桜しべ降る”って春の季語なん?私、初めて知ったかも。めっちゃかっこいい句やと思う」
この句の良さが今の私には十分わかる。
ー終わりは、始まりなんだ。
笑った祖母の頬に一瞬、桜餅のようにやわらかなピンクがさした。
それが祖母の辞世の句となった。
春。松山城の桜がいっせいに咲き、花の雲となり、雪のように散っていく。山は笑い、鳥は囀り、そして風は光る。
俳句のまち松山には春が一番似合うと言ったのは祖母だった。もしも私が俳句を教わっていなかったら、今こうして松山に住む幸せをここまで感じることができていなかったかもしれない。
私は自転車から降りて伸びをする。
おばあちゃん。私、おばあちゃんの後輩になったんよ。
結局、俳句告白大作戦の甲斐むなしく(いや、あれで気づけという方が無理なのだけど)風早くんとは何もなかった。なかったが、中学卒業の日、私の心は今日のこの空のように清々しく晴れ渡っていた。もしも、またそんな機会(告白?)が来れば、勇気を出してもうちょっと前に踏み出そうと思う。そして、そんな気持ちになれたのも、祖母と歩んだこの一年があったからだ。
おばあちゃん、私はおばあちゃんの孫で本当に良かった。
ふう。
ところで、おばあちゃん。おばあちゃんが亡くなる前日にポツリと呟いた言葉に、俳句作りでみっちり鍛えられた私の想像力は刺激されっぱなしです。
ーせいいちろうさんー
祖母は確かにそう言った。「せいいちろうさん」と。おじいちゃんの名前は「きよし」。母はちょうど詰所で看護士さんと話してたからこのことは私以外誰も知らない。これは祖母と私だけの秘密にしておくつもりだ。
一応、「せいいちろうさん」は私の中で、祖母が戦時中に思いを告げられなかった人ということにしておこうと思って、あっ。
携帯メールの着信音。
ん?え?ええっ?!
《風早です。なんか、いきなりのメールですまん。うちのばあちゃんが三浦さんとこの亡くなったおばあちゃんの県女の後輩だったらしくて、昔話がしたいから今度うちに遊びに来ないかって。あ、このメアドはなんかメイドからの土産とかで、三浦さんとこのおばあちゃんからうちのばあちゃんに・・》
桜しべがはらりと舞い落ちた。
私の物語は今始まったばかりだ。 了
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
文化・ことば課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館5階
電話:089-948-6634