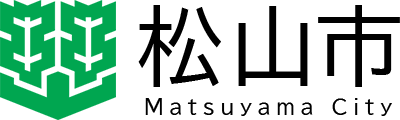第15回坊っちゃん文学賞ショートショート部門大賞「オトナバ―」
更新日:2018年3月1日
PDFファイルでもお読みいただけます。
「オトナバー」 塚田 浩司
そのバーに初めて入った時の事は覚えていない。場所もはっきりとは分からない。でも隆史が「バーに行きたいな」そう念じて歩いているとひょいと見つかるのだ。
入り口に看板はなく、木製の所々剥げている扉があるだけ。その古めかしさが何とも味わい深く、趣を感じる。扉を開けるともうひとつ扉があり、そこには注意書きが書かれている。
その一、バーの中では紳士であれ。
その二、年齢制限はありません。
その三、代金はお気持ちで結構です。
変わったバーだ。特に最後の「代金はお気持ちで結構です」とはかなり珍しい。なので、隆史はいつもお気持ちとして全財産の五百円をマスターに渡している。少ないかなと思ったが「またお越しください」とマスターは優しくほほ笑んでくれる。その笑顔に甘えて隆史はちょくちょくこのバーに顔を出す。マスターに愚痴を聞いてもらうのが隆史にとっては何よりも心の支えになっているのだ。それにバーというのは大人になった気分にさせる。少し背伸びをし、
緊張して店に入る。店内の香り、落とした照明、BGMのジャズ、ピンと張りつめた空気込みで雰囲気を楽しむ。それがバーの醍醐味なのだ。
この日は先客が二人いた。気の弱そうな中年男と美しく着飾った女だ。
「やあ」隆史はマスターに会釈をしてカウンターのいつもの席に腰を下ろす。そして「いつもの」とクールに注文した。マスターは「かしこまりました」とうなずいた。
「マスター聞いてよ。前に話した鈴木君がこっちから視線を投げかけたりして気を引こうとしているのに何のアクションも起こしてくれないの。もう待ちくたびれたわ」
着飾った女がマスターに恋愛相談している。ここでは客の話を聞いているだけでも楽しい。
「もう、こっちから告白しようかな」女はグラスの氷を見つめながら、ため息をついた。
「そうですね。待っているのはお辛いでしょう。でしたらそれも良いのかもしれませんね」
「マスターもそう思う?」女はグラスに口をつけた後、いたずらな笑みを浮かべた。
「ところでマスターはどうなの? 女性に積極的にいける方?」
マスターは女の問いに苦笑いを浮かべた。
「そうですね。私がお客さんくらいの年齢の時は、それはもう奥手で、好きな女性に声を掛けるなんて全く出来ませんでしたよ。その鈴木さん、もしかしたら……」
「もしかしたら?」女は首を傾げた。
「若い時の私のようなタイプかもしれません。奥手なんじゃないですか?」
「じゃあ、諦めない方がいいかなあ」
女の口元がほころび、マスターに同意を求めるように見つめると、マスターは「はい」と優しい笑顔を向けた。すると女は勢いよく立ち上がり「マスター帰るね」そう言って颯爽と店を後にした。その時、女のなびいた長い黒髪から甘い良い香りがした。
「すみません。お待たせしました。どうぞ」
隆史の前にオレンジのカクテルを置くとマスターは頭を下げた。隆史は華奢で細長いグラスに口をつけた。濃いオレンジが苦い。
でもそれが癖になる味だ。
「マスター。前、どこまで話しましたっけ?」
気の弱そうな中年男がマスターに話しかけた。
「確か、組織の大役を引き受けて、これからが不安だと。期待に応えられるか不安だと」
「はい。不安が的中しました」中年男はグラスの氷を転がした。
「やっぱ自分は人の上に立つ器ではなかったのかもしれない」
中年男性は俯いた。するとマスターが手を止めた。
「器ですか」マスターはポツリと言った。そして一枚のスープ皿を取り出しカウンターに置いた。
「ちなみにこの器は落としたら割れますし、沢山のお水を注げば溢れます」
どうしてそんな当たり前のことを言うのだろう。隆史はカウンターに置かれた皿を見た。中年男もきょとんとした顔をしている。構わずマスターは話を続けた。
「大役を任されたという事は期待されたという事ですよね? 今はその期待とか重圧が重くて辛いですよね? どんなに大きな会社の社長さんもそうですが、最初から社長の器なんてないんですよ。それが期待されて、重圧に耐えているうちに社長の器が出来上がるんです」
マスターの言葉に中年男は何か思いつめたように遠くを見た。そして
「つまり、僕も頑張って耐えれば、大きくて頑丈な器が出来上がるということですか?」
マスターはこくりと頷いた。すると中年男は力強く「よし、頑張るか」と口にしながら首を縦に振った。中年男の目に力が湧いて来たような気がした。
「でもね、もし、それでもダメだなって思ったら逃げたっていいと思いますよ」
マスターは包み込むような笑顔を浮かべた。
「ありがとうございます。頑張るって言った後にこんなこと言ったら変なんですが、おかげで気が楽になりました」
気の弱そうな中年男はもう気の弱そうな男ではなくなっていた。中年男は立ち上がり代金を払い、「ごちそうさまでした」と言い背を向けた。
「どうもありがとうございました」
マスターはカウンターから出て、中年男の背中が見えなくなるまで深々と頭を下げた。
バタンと扉が閉まる音がした。マスターはカウンターに戻り、中年男のグラスを下げ、テーブルを拭いた。店内は隆史とマスターの二人きりになった。
隆史は気になった。今まで何回かこの店に来たが、「ありがとうございました」とは言われたことがない。そんなことを考えているとそれが伝わったのかマスターが口を開いた。
「あの方はね、もう来ないですよ」
「えっ?」
「もう迷いが消えていましたから。もうこのバーにくる必要がないんですよ」
確かに隆史の目から見ても中年男の顔は店を出る時、あきらかに別人のようだった。
「でも、マスター寂しいね」
「さあ」マスターはごまかすように言い、磨いたグラスを棚にしまった。あの中年男は相談して自分なりの答えを見つけたんだな。隆史はそう思った。
「お飲み物はいかがですか?」空になったグラスを見てマスターが尋ねた。
「同じものを」
「かしこまりました」
マスターはグラスに大きな塊の氷を入れ、慣れた手つきで生のオレンジを搾っている。
「ねえ、マスター」
「はい」マスターは手を動かしたまま返事をした。
「もうそろそろヤバそうなんだ」
マスターは「そうですか」と返事をした。
そして「はい。どうぞ」と言い隆史の前にカクテルを置いた。目の前に置かれたカクテルを隆史は手に取った。でも口をつけない。
「母さんが、もしかしたら死んじゃうかもしれないんだ。オレは心配で心配で勉強にも身が入らないし友達と遊ぶ気にもならないんだ」
一瞬、間が空いたが「そうですか」と表情を変えずに言った。
「母さんに万が一のことがあったら耐えられるかどうか」
マスターの口元を見ると、今度は「そうですか」とすら言わない。
「早く大人になりたいんだ。マスターどうすれば早く大人になれる?」
この言葉にマスターが首をひねった。「どうして大人になりたいんですか?」
「どうしてって……」隆史は言葉に詰まりながらも自分の思っていることを話した。
「だって、大人になれば悲しくないんでしょ? 悲しいことにも耐えられるんでしょ? オレがこんなに悲しいのもまだ子供だからでしょ? だって父さんは母さんが病気で大変なのに何事もない顔して会社に行っているよ。最近、忙しいって母さんは言ってたけどさあ」
マスターは返事をしない。店内にはジャズが響き渡る。この泣いているようなトランペットの音はどこかで聞いた覚えがある。ジャズ好きな父さんが聞いていたのかもしれない。
「さっきのお客様見ましたよね?」
「重圧で悩んでいるおじさん?」
「そうです。それからその前にいたお嬢さん」
隆史はあの綺麗な女を思い出した。
「それがどうしたの?」
「あの二人もあなたと同じ小学生ですよ」
「えっ? そんなわけないよ。だっておじさんと綺麗な大人の女の人だったよ」
隆史が目を丸くしているとマスターは手鏡を渡してニヤリとした。手鏡を手に取り、覗き込んだ隆史は驚いた。そこにはいつもの自分ではなく、大人の顔をした自分がいたからだ。そして掌を見た。それは思ったよりも大きくて皺が深く刻まれた大人の手だった。
「バーは人を大人にするんです。だからここでは姿を変えているんです。でもね」
「でもなんですか?」
隆史が尋ねるとマスターはまた微笑んだ。
「小学生も大人も悩みなんてほとんど一緒なんですよ。あの男性は小学校の児童会長になったんです。本人はあまり乗り気ではなかったようですが、推薦されて仕方なしだったみたいです。その重役を果たせるかどうか自信がなかったんですね。また、その前にいた女性は恋の悩み。これは子供も、何ならお年寄りも同じなんです。恋するって何歳でも同じなんです。不安なんです、怖いんです」
そういうものなのか。恋についてはまだ分からないな。隆史はそのまま耳を傾けた。
「大人だって不安なんです。悲しい時は悲しいんです。泣きたい時は泣くんです。でもね、どう過ごすかなんです。あなたのお父様も不安なんです。悲しいんです。あなたと一緒です」
「父さんも一緒?」
「そうです。お父様も悲しみに暮れるだけではなく、今できることをしようと必死なんです。そうやって生きていくんです。生きていくしかないんです」
隆史は言葉を失った。そしてここ最近の自分の無気力さを思い出して情けなくなった。自分は母さんのことを言い訳にしていたのだ。そんな自分を母さんは喜ぶはずもないのに。
「マスター帰ります」隆史はいてもたってもいられなくなり立ち上がった。そして握りしめていた五百円玉をカウンターに置いた。
「また来ますね」隆史が頭を下げるとマスターは渋い顔をしただけで無言だった。
隆史が不思議そうな顔でいると、マスターがカウンターから出てきた。
「どうもありがとうございました」
深々と頭を下げるマスターに隆史は背を向けた。ドアノブに手を触れた時、振り向こうかと思ったけれど、名残惜しくなりそうだからそれはやめた。
どのくらいの時を過ごしたのだろう。バーから出ると外は夕暮れ時だった。
バーで見た大人の自分を思い出し、隆史は掌を見た。それはいつも通りの小さな掌だった。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
文化・ことば課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館5階
電話:089-948-6634