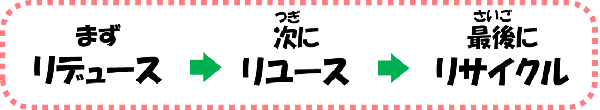ごみ収集車(パッカー車)の写真
ようこそ、清掃課のキッズページへ!
清掃課では、次のような仕事をしています。
- 家庭から出されたごみを収集する
- ごみを減らしたり、リサイクルをするように呼びかける
- ごみ置き場を新しく作ったり、移動させたりする申請を受付ける
- 死んでしまった動物を収集する
ごみを種類ごとに分けて出すことを「ごみを分別する」といいます。
ごみをきちんと分別すると、それぞれの種類ごとにリサイクルをすることができます。
松山市のごみの分別は、次の8種類です。
燃やすごみのことです。
- 生ごみ、布・革製品、リサイクルできない紙やプラスチック製品など

このマークがあるペットボトル。
※ボトル本体のみ。キャップやラベルは「プラスチック製容器包装」です。
- お茶やジュースのボトル、調味料のボトルなど

中身を使ったあとにいらなくなるプラスチックでできた容器(うつわ)や包装(つつむもの)のことです。
このマークが表示されています。
- パンやお菓子の袋、お肉やお魚が入っていたトレイ、シャンプーのボトルなど
「紙類」はさらに次の4種類に分けます。
- 新聞紙・折り込みチラシ
- 牛乳パックなどの紙パック
- 段ボール
- 本類・雑がみ
※「雑がみ」とは、「新聞紙・折り込みチラシ」、「紙パック」、「段ボール」、「本類」以外の紙のことです(ティッシュの箱、お菓子の箱、ふせんなど)。小さな紙でもリサイクルができますので、きちんと分別して「紙類」で出しましょう。
びん・缶、刃物、鉄・ガラス製品などです。
- ジュースの空きびんや空き缶、スプレー缶、包丁、なべ、フライパンなど
土や石でできたものなどです。
- 土・石・ブロック、お茶わん、植木鉢、乾電池など
水銀が使われている製品のことです。
- 蛍光灯・電球、水銀を使っている体温計、ボタン型電池など
ごみ袋に入らない大きなものや、電気製品などです。
- たんすや机などの家具、電子レンジや掃除機などの電気製品、自転車、たたみなど
ごみを減らすキーワード「3R(スリーアール)」
みなさんは「スリーアール」という言葉を聞いたことがありますか?
ごみを減らすための行動を表す「リデュース(Reduce)」、「リユース(Reuse)」、「リサイクル(Recycle)」という3つの言葉をあわせて「スリーアール」といいます。
3つの言葉の意味は次のとおりです。
リデュース(ごみを減らす、ごみを作らない)
- 本当に必要なものだけを買う
- ものを大切にする・長く使う
- 食べ残しをしない
リユース(捨てずに、繰り返し使う)
- シャンプーや洗剤などは、詰め替え商品を使う
- リサイクルショップやフリーマーケットを利用する
- 壊れても、修理をして使う
リサイクル(資源としてもう1度利用する)
- きちんと分別してごみを出す
- リサイクルで作られた製品を買う
スリーアールには、優先順位があります。
まずはごみのもとを作らないこと(リデュース)が1番大切です。
そして使わなくなってしまったものは、すぐ捨てずに人にゆずったり、他に使い道はないか考えましょう(リユース)。
最後にどうしてもごみになってしまったときに、きちんと分別して資源として再利用(リサイクル)するように心がけてください。
この順番をしっかり覚えて、生活の中でスリーアールを実践してみましょう。


![]()